猫のいる家:猫と玄関

玄関ドアを開けた瞬間に、
猫が外に飛び出していってしまう、という事件を良く聞きます。
玄関とつながる空間には、扉をつけてワンクッションを置く、
ということで対策ができます。
扉を付けてしまうと、帰宅時に猫に出迎えてもらえない、
という感想もあると思います。
扉をガラスにすれば、ガラス越しですが、
出迎えてくれる猫を見ることができます。

玄関ドアを開けた瞬間に、
猫が外に飛び出していってしまう、という事件を良く聞きます。
玄関とつながる空間には、扉をつけてワンクッションを置く、
ということで対策ができます。
扉を付けてしまうと、帰宅時に猫に出迎えてもらえない、
という感想もあると思います。
扉をガラスにすれば、ガラス越しですが、
出迎えてくれる猫を見ることができます。

猫の場合はフローリングで滑る危険性は低いため、
犬ほどフローリングを心配する必要がはありません。
猫の場合気を付けたいのは、「爪の引っかかり」です。
歩行時、爪を収納していますが、遊びの際には出る頻度も多く、
老猫になると、爪が常に出っ放しになることもあります。
もし床材にカーペットを使用する場合は、
生地をループパイルのものより、カットパイルの方が、
猫にとって快適になります。

ねこのトイレの設置ポイントについて
書いてみます。
まずねこ用トイレのサイズ感ですが、
「体長の1.5倍以上」が推奨とされています。
体長40㎝のねこの場合には、
600mm以上の大きさが必要になります。
また、飼い猫の頭数+1か所は、
余分に用意することも推奨されています。
多頭飼育の場合は、置く場所を分散させた方が良い場合もあります。
ねこにとっては、
ご家族の往来が少なく、静かな場所がいいものですが、
飼い主が、頻繁にチェックのできる「目の届きやすい場所」
であることも、両立させたいです。
人間のトイレの空間に、
一緒にねこトイレスペースを作ったり、
階段下の空いている空間に、ねこ専用のトイレ空間をつくる
というアイデアもあります。

大阪:吹田の家のキャットウォークを検討しています。
階段からはじまり、2階のLDKをぐるっと1周できるようにしています。
4匹いるねこの居場所になればいいなと思っています。

ねこにとって、トイレの環境は、
健康と精神面を左右する、重要な場所です。
また、飼い主にとっても、飼い猫の健康状態を確認したり、
こまめに掃除したりと、頻繁に訪れる場所となります。
ペットショップなどで購入できる猫トイレには、
ドーム型のものだったり、オープン型のものだったりがあると思います。
ドーム型は、排泄物が外から見えにくく、
臭いが漏れにくいという人間側のメリットがありますが、
猫にとっては、すぐに逃げられるような、
オープン型を好む傾向があります。
ねこ自身がトイレを嫌いになってしまうと、
トイレを我慢してしまって、病気につながるなどのリスクにもつながります。
・飼い猫の頭数+1台は余分に設置する方が良い
・ねこが中で方向転換できる十分な広さ
・飼い主がチェックしやすい場所に設置する
・暑さ&寒さ対策
・臭い対策
・床の掃除のしやすさ
・掃除用具やトイレ用品の収納
などが、猫トイレを設置する場合のポイントとなります。
この他にも、サイズであったり、設置場所など
気を付けたいポイントがあるので、
またブログで、報告していきます。
「犬のいる家・猫のいる家」過去事例
https://aplan.jp/works/category/dogcat/

ねこは、爪のメンテナンス、マーキング、リフレッシュのため
爪とぎを行います。
・玄関や窓の近く
・ドアの近く
・柱や部屋の出隅など出っ張りのある部分
・居場所から目につく場所
などが、ねこが爪を研ぎたくなる場所と言われています。
この壁には、ひっかき傷を作りたくなかったり、
ソファやベッドなど、傷つけてほしくない場所では爪を研がせないよう、
適切な場所に、ねこの爪とぎ場所を作ることが必要になります。
ねこの起床時や食後など、
「何かをした後」に、爪を研ぐことが好きなので、
ごはんを食べる場所、水飲み場、寝る場所の動線上に、
用意をしてあげることで、他の場所での爪とぎを、
抑制することができます。
「犬のいる家・猫のいる家」過去事例
https://aplan.jp/works/category/dogcat/
大阪:吹田の家のキャットウォークを検討しています。
家全体で猫の居場所として、1階と2階のつながりを考えたいと思いました。
階段が途中からキャットウォークに変化していきそのまま2階のLDK全体を
回遊できるように検討しています。


ねこは意外と器用に手を使います。
机の上に置いているものを、ちょいちょい、と触って、床に落とすような行動を、
見たことがあるかと思います。
そんな器用なねこは、レバーハンドルの付いた扉、を開けることができます。
ハンドル部分に手をかけ、ぶら下がり体重をかけ、
意図も簡単に、開けてしまいます。
ねこが入ってほしくない部屋、外に出てほしくない部屋には、
ハンドルタイプではなく、握り玉のような、人間の手のひらで掴んで、回す
という動作が必要なものにするのが、最適です。
「犬のいる家・猫のいる家」過去事例
「家族にねこ・いぬがいます」という建築主が、
最近多くなってきています。
猫のいる家、犬のいる家について、
定期的に、ブログにてお知らせしていこうと思います。
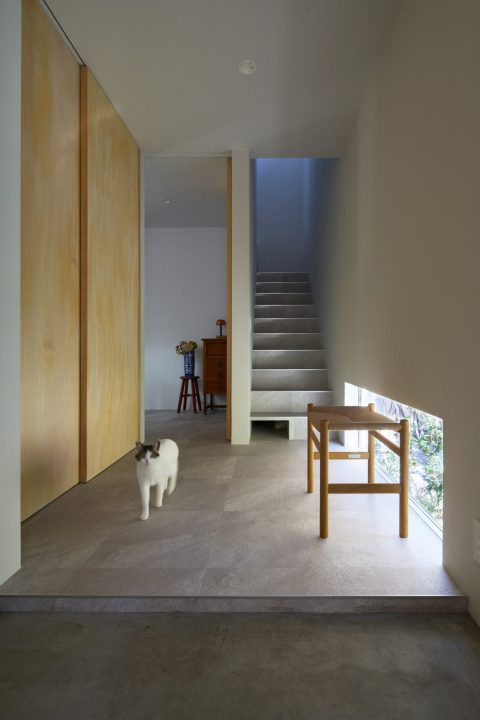
今回は「猫のいる家:生態について」、まとめます。
ネコ科の動物は、基本的には単独で行動し、狩りを行う動物です。
自分の身は自分で守るという意識から、
警戒心や臆病さが強い傾向があります。
なので、大きな音や見知らぬ来客などに、恐怖し、
家の中の「高い場所」や家具の下などの「狭い場所」に、
逃げ込むことが、よくあります。

手の届かない、高い位置にのぼり、
下にいる人の様子を、じっと観察しています。
本当に手の届かない高い空間を作ってしまうと、
万が一、地震のときなどにびっくりして、入り込んでしまい、
救出ができない、となるケースもあるので、
設計には注意が必要です。
ただ、ねこにも性格があります。
人懐っこい猫や、全く他人には触れあいたくない猫、
子どもからは逃げる猫など、さまざまですので、
それぞれ、飼っている猫に合わせて、設計していくのも大切です。
「犬のいる家・猫のいる家」過去事例
https://aplan.jp/works/category/dogcat/

東京:武蔵野の家 をホームページに掲載しました。
プラン検討にあたっての中心的な内容に猫達が動きまわって、その動きを眺められたらという話しがあり
どのように空間に取り込むかが大きな課題のひとつとなりました。
敷地形状が旗竿地という特徴を活かすかたちで、アプローチを道路境界から竿部分に小道をつくり
その小道が玄関を抜け、クネクネとまっすぐ家のなかのサンルームを通り抜ける案を提案しました。





































